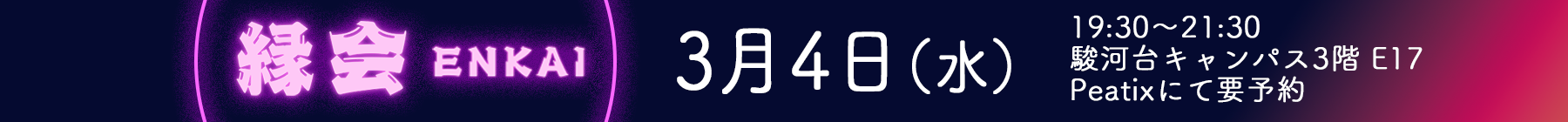No.28

麻酔科医 YouTuber
みおしん さん(デジタルハリウッド大学院)
このインタビューは、2020年8月当時の内容です。
職業は、麻酔科医のYouTuber。医師として模索する新しい発信の形
- Q
- さっそくですが、みおしんさんの現在のお仕事は?
- A
- いろんなことをやりすぎていてどこから伝えればいいのか悩ましいですが、分かりやすくお伝えすると、女医のYouTuberをやっています。
- Q
- 女医Tuber?
- A
-
そういうことになりますね(笑)。現在は麻酔科専門医として千葉県の鎌ケ谷バースクリニックに勤務しながら、WiTH PAiNという事業を起こし、YouTubeやnoteなどを使って発信活動をしています。
といっても、大学を卒業してからの8年半は病院で勤務するいわゆる「お医者さん」。2019年4月に麻酔科の専門医を取得したのち8月にフリーランスとして独立し、医療福祉分野とエンターテイメントを掛け合わせた活動を始めました。フリーランスとしての経験は1年ちょっとで、その活動のなかの1つがYouTuberということです。
- Q
- 発信を始めた理由は?
- A
- きっかけは、自分が「線維筋痛症(せんいきんつうしょう)」だとわかったことでした。線維筋痛症とは、原因不明の強い痛みや倦怠感に襲われる病気です。
わたしの場合は、学生時代から異常な疲れやすさがありました。研修医として働くようになってからも、整骨院、鍼など疲労回復に良いとされるありとあらゆる場所に行き、定期的に麻酔科ペインクリニックにも通院しながら勤務に当たっていたんですよね。
その症状に「線維筋痛症」という診断が降りたのは、麻酔科の医師として働いていた2018年。強い倦怠感を感じるようになった中学時代から数えて、20年近くの年月が経っていました。
自分の病気が線維筋痛症だとわかったとき、インターネットで検索をしてみたんですよね。すると出てくるのは「痛い」とか「辛い」とか、そういう患者さん自身の体験ばかりで。2017年時点で、線維筋痛症の推定患者数は人口の1.7%、200万人もいると言われています(※)。それだけたくさんいるはずなのに、正しい情報を手に入れるのは本当に難しい。そのことに疑問を感じるようになったんですよね。
【参考文献】
※一般社団法人線維筋痛症学会・国立研究開発法人日本研究開発機構線維筋痛症研究班(2017)『線維筋痛症診療ガイドライン』
- Q
- なるほど。世の中に情報が少ないなら、自分が発信しようと?
- A
-
そうですね。加えて、病気のことをなかなか理解してもらえないという自分自身の体験も、発信活動を始めたきっかけの1つになっています。
線維筋痛症の診断が下りたあと、自分の周りの人にはそのことを伝えるようにしていました。多くの同僚や友人は病気に対しての理解を示してくれました。ですが、痛みに関するプロであるはずの麻酔科の医師だけが「それは気持ちの問題だ」となかなか受け入れてくれなかったんです。
「線維筋痛症を知識として知っているからこそ、イメージが先行して受け入れてくれないのかもしれない」。このとき、わたしの中にそんな仮説が立ちました。
線維筋痛症は脳の炎症による身体的な病気で、決して気持ちの問題だけが原因でおこるものではありません。けれど、インターネット上ではそういった正しい情報を得るのは難しく、専門家である医師がこの病気について誤解していることすらある。
それなら、線維筋痛症についての正しい知識を発信することが、医師であり患者でもあるわたしの使命なのではと感じました。その2つのキッカケから、発信活動をスタートしています。
デジタルハリウッド大学院入学のキッカケは、”とがった人たち”との出会い
- Q
- デジタルハリウッド大学院を知ったキッカケを教えてください。
- A
-
以前、ニコニコ超会議で「日本うんこ学会」が制作した「うんコレ」というソーシャルゲームを見かけたんですよね。トイレの向こうの世界を守るために、敵を倒すっていうちょっと変わったゲームだったんですけど(笑)。
うんコレのアカウント単独で運用開始となりました。いよいよな感じです。
こっちの日本うんこ学会アカウントはよりストイックにうんこの話と、たまに役立つ健康情報を発信していけたらと思います。両者共によろしくお願い申し上げます。 https://t.co/AH5rz0wJtW
— 日本うんこ学会 (@unkogakkai) August 27, 2020
それで「日本うんこ学会って一体何をやっている団体なんだろう?」って調べていくと、彼らが目指しているのは大腸がん検診の普及と予防医療の認知拡大。それを「うんコレ」などの楽しいコンテンツを通してユーモラスに世の中に届けているということがわかってきました。
そして、日本うんこ学会の中にデジタルハリウッド大学に関わる人たちがいたんです。そこからさらに、とがったこと・面白いことをやっている人たちをたどっていくと、多くがデジタルハリウッド大学の卒業生や在学生でした。
- Q
- そこからどのように入学に至ったのでしょうか?
- A
-
デジタルハリウッド大学の卒業生や在学生が活躍する姿を見て、「ここでならやれることがあるかもしれない」と思ったんですよね。
今まではいち医療従事者であり、デジタルの領域についてはまったくの無知。YouTubeの発信も手探りでした。けれど、これだけたくさんの人がいろんな面白いものを生み出しているデジタルハリウッド大学でなら、自分もやれることがあるかもしれない。ここで挑戦してみたい、と思ったんです。
- Q
- 実際に入学してみていかがですか?
- A
-
入学当初の目的はデジタルコミュニケーションやICTについて学ぶことでした。けれど入学してみたら、「プロデュース能力開発」や「クリエイティブ特論」の授業が面白くて。
たとえば、「プロデュース能力開発演習」の授業は団子3兄弟をプロデュースした吉田就彦(よしだなりひこ)先生や論理的かつ自由な発想を引き出す佐々木先生が担当してくださっているんですよね。流行るコンテンツを生み出してきた人から直接話を聞けるのは本当に面白いですね。
- Q
- 他に印象に残っている授業はありますか?
- A
-
サイバーエージェントで活躍している二宮先生と中橋先生が担当してくださった「クリエイティブ特論」では、最新の広告事情を詳しい事例付きで教えてくれました。
杉山学長自ら講師をしてくださった「デジタルコミュニケーション原論」では、インターネットが生まれて普及するまでの歴史や、スティーブジョブスや落合陽一さんにフォーカスした授業で魅了してくれました。
それらの授業を受けて「自分がやろうとしていることが間違っていない」と感じるようにもなりましたね。実際にYouTuberとしての活動に反映できているかは自分ではまだわからないけれど(笑)。
いたみも、わくわくも、一緒に。「WiTH PAiN」に込めた思い

- Q
- インタビューの冒頭で、発信活動は「WiTH PAiN」という事業の一環として行われているというお話をうかがいました。どんな事業なのでしょうか?
- A
- WiTH PAiNでは、YouTubeやnoteなどのSNS発信のほか、カメラマン、モデル、歌手など多くの活動に取り組んでいます。キャッチコピーは「いたみも、わくわくも、一緒に」。いたみによる偏見や生きづらさが存在しない、思いやりのある世界を目指しています。
- Q
- 「いたみをなくそう」ではなく、「一緒に」?
- A
-
そうです。痛みはないほうが嬉しいけど、それを完全になくすのはどうしても難しいですよね。だからこそ、それを否定するのではなく「一緒に生きていこう」というマインドになってくれたら嬉しいなと思って。
いたみと闘う患者さんってどうしても、「この病気が治るまでは楽しんではいけない」「病気を治すことにだけに力を尽くさなければ」って思ってしまいがちなんです。でも本当は、遊びや好きなことのなかに”自分が歩みたい人生のヒント”は転がっています。だからわたしはWiTH PAiNの活動を通して、堂々と遊ぼう!好きなことをしよう!って伝えたいんです。
- Q
- 「WiTH PAiN」という名前も、「いたみといっしょに」という思いがそのまま表れたものなのですね。
- A
- そうですね。「WiTH PAiN」の「i」を小文字にしたのにも、理由があって。大文字は元気な人、iは立場の弱い人・いたみを抱えて生きている人を表しています。それぞれが違う場所で生きていくのではなくて、立場の弱い人・いたみを抱えて生きている人も、元気な人とまざって生きていけるんだよ、っていうことを伝えたいなと思いました。
- Q
- 元気な人と立場の弱い人が混ざって生きていくためには、社会の側(がわ)も少しずつ変わっていく必要があるような気がしています。
- A
-
おっしゃる通りですね。慢性的ないたみと闘う患者さん患者さんたちの多くは、働く、友だちをつくる、趣味を見つける……そんな「ありきたりな普通の日々」を望んでいます。
一方で、「慢性的ないたみ」は、どうしてもほかの障がいや病気と比べると地味で埋もれがち。そのため、いたみと闘う多くの患者さんがいるということを一般の人はあまり知らず、患者さんと一の間に境界が生まれてしまうこともあるんですよね。だからわたしは、その境界をなくして、元気な人と立場の弱い人をつないでいきたいと思っているんです。
- Q
- 境界をなくして、つないでいく?
- A
-
そう。実は、WiTH PAiNのサブコンセプトも「We gotta borderless!」(僕らはボーダーレスを手に入れた)。もともとは友人の佐伯ユウスケが社団法人WITH ALSのために書き下ろした楽曲のタイトルだったのですが、2018年に自分の病気がわかったときから「絶対にWe gotta borderlessの世界を広げるんだ」という強いがあって。WiTH PAiNを立ち上げたときにサブコンセプトとして起用させてもらったんです。
これはわたしの解釈ですが、実は世界はすでにボーダーレスになっていて、つながっていると思うんです。でも、みんなまだそのことに気づいていない。
わたしがWiTH PAiNを通して発信活動をすることで、みんなが「世界はすでにボーダーレスになり始めているんだ!」と気づいてくれたらいいなと思うんです。そしてその気づきによって、立場の弱い人と元気な人との間になんとなく生まれてしまっている「境界」もなくしていきたい。
そのために、まずは自分がインフルエンサーとしての力、その名も「みおしん力」をつけて、より多くのことを世の中に発信できたらいいなと思っています。
みんなが実現したい「ハッピーな世界」を混ぜ合わせる

- Q
- これから力を入れたい活動はありますか?
- A
-
この夏から取り組んでいるのが「コミュニケーションの表現や場所を広げること」です。
それに大きな可能性を感じているのが「手話」。新型コロナの流行でみんながマスクをし、口頭でのコミュニケーションがとりにくい今こそ、手話という文化が大きな役割を担うのではないか、と考えるようになりました。きっかけは、2020年の4月に三浦大知さんやAIさんの歌ったBe Oneという歌を、ファンの皆さんが手話歌にして発信していたこと。当時は非医療従事者の方々になかなかSTAY HOMEを受け入れてもらえず、「所詮医療従事者の声は届かないのか…」と私自身が荒みかけていたときでした。
そんなときにBe Oneを見て、ものすごく感動したんですよね。手話が判らなくても伝わってくるものがたくさんあったし、難しそうな手話も音楽と組み合わせるとすんなり覚えられる。孤立しやすい今、「おうちにいて」と訴えるだけではだめだと気づいたんです。
感染が収束するのをただ待つだけではなく、カラダも心も元気で楽しく過ごしてほしいな、と思うようになり、メディアアーティスト授業の「え、リモートじゃないの?展」でも、それにちなんだ展示をさせていただきました。
- Q
- これから手話歌を披露される機会はありますか?
- A
- 2020年の10月18日にホッチポッチミュージックフェスティバルで、ついにリアルでお見せする機会があり、現在猛特訓中です!しばらくは、手話歌と、映像、音楽の力で色んな方々を巻き込んでおもしろいものを創っていきたいと思っています。
- Q
- 今後校友会で実現していきたいことはありますか?
- A
- ファッションテックラボに所属しているので、感覚が過敏な人や洋服を重たく感じやすい人にとっても着心地の良いファッションを提案していきたいですね。あとは、環境にやさしい製品を広めたり、食事療法について考えたり……個人としてやりたいことはたくさんあるので、校友会にそれらを得意分野としている方がいたらぜひご一緒したいです。
わたしが思い描いている未来の世界は、皆さんが実現したい「ハッピーな世界」と最終的に合流できるものだと確信しています。校友会のコミュニティを生かして、みんなの中にある「こうなったらいいな」を、力を合わせて実現していきたいですね。